Uncle Tungsten
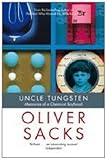
価格: ¥1,448
カテゴリ: ペーパーバック
ブランド: Picador
『レナードの朝』や『火星の人類学者』など、優れた医学エッセイで知られる脳神経科医オリヴァー・サックスが化学に心酔した少年時代を振り返ったエッセイ集である。19世紀半ばにロシアからイギリスに移住したユダヤ人の孫として生まれた著者は、献身的な医者を両親に持ち、化学、物理、生物学に通じる叔父や叔母のいる理系一家で育った。なかでも、とりわけ興味をそそられたのが金属だった。周囲の薫陶を受けつつ、やがて少年は華麗な変化を巻き起こす物質たちの虜(とりこ)になってゆく。
とにかく面白い――本書を読み終えた感想はこのひと言だった。本書のテーマは無機化学だ。無機化学というといかにも無味乾燥な響きがして、実際、味気のない啓蒙書が多いものだが、著者が描き出す世界はこの上なく豊かに彩られていた。電球のフィラメントを作る会社経営者であるタングステンおじさんをはじめ、具体的で博物学的な知識を教えてくれる面々はまるで生きた博物館だ。水銀に浮くタングステンの比重に驚嘆したり、猛毒の塩酸と苛性ソーダを混ぜた溶液を飲んでみたり、サウス・ケンジントンの科学博物館に飾られた周期表の前で何時間も夢見心地で過ごすなど、みずみずしい感性の少年が実験に挑み、物質の魅力にとりつかれてゆくさまは、まさに化学をめぐる冒険であり、読む者は引き込まれずにいられない。
何よりも、化学を既知のものとして教科書的に説明するのではなく、“センス・オブ・ワンダー”をもって自然の神秘とその謎解きをつづっているのが本書の魅力の源泉である。加えて、元素の発見から周期表、放射線、量子化学まで、時代背景とともに化学の発展を紹介する手法はわかりやすいし、随所に織り込まれたユニークで優秀なサックス家の人々や偉大な科学者たちのエピソードは読者を飽きさせない。とかく敬遠されがちなサイエンスの、しかも無機化学というテーマをこれほど面白く描き、その本質をしっかり伝える著者の力には完璧に脱帽だ。(齋藤聡海)
関連商品