Reminiscences of a Stock Operator (Wiley Investment Classics)
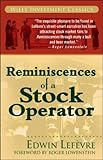
価格: ¥2,402
カテゴリ: ペーパーバック
ブランド: Wiley
関連商品
我、一人。
★★★★★
ローウェンシュタイン氏の「まえがき」がなければこれがリバモアに取材した本だとは少なくともシロートは気づかないでしょう。本文でリバモアにあたる相場師の語り部は「リヴィングストン」となっています。英語は時代を反映して多少古風で、語り口は紳士的です。
「相場無関係者にとって得るモノはあるか?」ですが、さてさて。一読しての感想は「なんとまぁキツイところにいる人であろうか」でした。いかなる時代のいかなる社会でも、「ただ一人」で成立する生業なんてのはいくつあるでしょう。「孤高の芸術家」だって「客」が必要なんである。家柄も学歴もコネもない貧しい少年が、誰に阿るでもなく、誰に何を乞うでもなく、誰も必要とせず、「相場」だけに向き合って頭脳だけで金を稼いでいく、というのは文化人類学的(?)にかなり異様な営みに思えます。人間本能に反しているのではとさえ。そのせいかどうか、途中から語り部の「リヴィングストン氏」が「市場」という「絶対的な現実」に帰依する僧侶かなにかのように思えてきました。
「リヴィングストン氏」にとっては相場こそが真実の場所だったのではなかろうか、というのはロマン的な読みが過ぎるかもしれませんが、天才級のダンサーはよく「現実社会よりも舞台の方にこそ『真実』がある」などと言います。我々の生きる社会は不透明が常態の答えのない場所である。正邪も善悪も曖昧模糊としたまま、感情と妄想と大小の偽りが互いに渦巻きながら時間ばかりが流れていく。しかし少なくとも相場においては、語り部は「right」と「wrong」の有無を言わさぬ強烈な感触に出会える。その透明で絶対的な瞬間と出会う為に、彼は自分を容赦なく客体化し、心を純粋運動するフイゴか何かのように鍛えていく。いやはや。
相場と縁のない一読者の愚考ですが、そういう場所でのみ充実する人間は幸せなのか不幸せなのか、これもまた答えのない問いです。
「相場無関係者にとって得るモノはあるか?」ですが、さてさて。一読しての感想は「なんとまぁキツイところにいる人であろうか」でした。いかなる時代のいかなる社会でも、「ただ一人」で成立する生業なんてのはいくつあるでしょう。「孤高の芸術家」だって「客」が必要なんである。家柄も学歴もコネもない貧しい少年が、誰に阿るでもなく、誰に何を乞うでもなく、誰も必要とせず、「相場」だけに向き合って頭脳だけで金を稼いでいく、というのは文化人類学的(?)にかなり異様な営みに思えます。人間本能に反しているのではとさえ。そのせいかどうか、途中から語り部の「リヴィングストン氏」が「市場」という「絶対的な現実」に帰依する僧侶かなにかのように思えてきました。
「リヴィングストン氏」にとっては相場こそが真実の場所だったのではなかろうか、というのはロマン的な読みが過ぎるかもしれませんが、天才級のダンサーはよく「現実社会よりも舞台の方にこそ『真実』がある」などと言います。我々の生きる社会は不透明が常態の答えのない場所である。正邪も善悪も曖昧模糊としたまま、感情と妄想と大小の偽りが互いに渦巻きながら時間ばかりが流れていく。しかし少なくとも相場においては、語り部は「right」と「wrong」の有無を言わさぬ強烈な感触に出会える。その透明で絶対的な瞬間と出会う為に、彼は自分を容赦なく客体化し、心を純粋運動するフイゴか何かのように鍛えていく。いやはや。
相場と縁のない一読者の愚考ですが、そういう場所でのみ充実する人間は幸せなのか不幸せなのか、これもまた答えのない問いです。