真夜中の足音
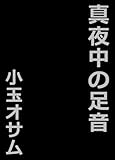
価格: ¥0
カテゴリ: Kindle版
あれはいつも真夜中のことだった。十代の終わり、家を出る少し前だ。いびきをかいて眠っていても、あの足音を聞くとはっきり目が覚めてしまった。暗い部屋の中に廊下の常夜灯の明かりが差し込んできて、私は布団の隙間から顔を出し、目をしばたかせるのだった。するとのっそりと、巨大な影が部屋に入ってくる。
「声を出すなよ」
息を殺した低い声だった。影は畳をミシミシといわせて私の布団をめくり、隣に潜り込んできた。酒臭い息の匂いがした。ごつい手が体を撫でた。
「いやだ」
私はかすれ声で言った。ごつい、煙草臭い手が私の口を押さえた。
「静かにしろ。声が出るなら、これで栓をしてやる」
………………………………………………………………………………
四十五になった主人公の私は二十数年ぶりに実家に戻ることになった。父と、年子の兄の二人で暮らしている家だ。
この数十年の間、見続けている奇妙な夢があるのだが、夢の内容は覚えていない。ただ同じ夢を見たという感覚だけが目覚めた時にある。それが淫夢であることはわかっていたが、実家に戻り、父、そして兄と暮らすようになってはじめて、夢の内容とその意味を知ることになる。
私は真夜中の足音をおそれていたのか、それとも待ちわびていたのか……。
初出『豊満』。官能サスペンス中年小説。
「声を出すなよ」
息を殺した低い声だった。影は畳をミシミシといわせて私の布団をめくり、隣に潜り込んできた。酒臭い息の匂いがした。ごつい手が体を撫でた。
「いやだ」
私はかすれ声で言った。ごつい、煙草臭い手が私の口を押さえた。
「静かにしろ。声が出るなら、これで栓をしてやる」
………………………………………………………………………………
四十五になった主人公の私は二十数年ぶりに実家に戻ることになった。父と、年子の兄の二人で暮らしている家だ。
この数十年の間、見続けている奇妙な夢があるのだが、夢の内容は覚えていない。ただ同じ夢を見たという感覚だけが目覚めた時にある。それが淫夢であることはわかっていたが、実家に戻り、父、そして兄と暮らすようになってはじめて、夢の内容とその意味を知ることになる。
私は真夜中の足音をおそれていたのか、それとも待ちわびていたのか……。
初出『豊満』。官能サスペンス中年小説。