日本語のしくみがわかる本
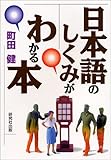
価格: ¥1,680
カテゴリ: 単行本
ブランド: 研究社出版
【セブン-イレブンで24時間受取りOK・送料0円!】 著者/訳者名:町田健/著 出版社名:研究社出版 発行年月:2000年11月 関連キーワード:ニホンゴ ノ シクミ ガ ワカル ホン にほんご の しくみ が わかる ほん、 ケンキユウシヤ 1861 けんきゆうしや 1861、 ケンキユウシヤ 1861 けんきゆうしや 1861 えっ!日本語の文法は間違いだらけだったの!?愛娘に「言語学者なのに、こんなことも知らないの!」と言われたことがきっかけだった。父は娘の持つ教科書や参考書をむさぼり読み、その文法解説のひどさに愕然とする。現在の日本語文法のどこが間違っているのか、またなぜおかしくなったのか、その実体が、えらく軽い口調で(笑)明かされる。 第1章 日本語の文法についてこれまでどんなことを教わってきたか(中学の「文法」文法がよくわからない原因「文節」はね、最初にさ、つまずくところなんだよ ほか)第2章 国文法はどのように考えられてきたか(「文節」の橋本進吉文節はいつも続けて発音さ
関連商品
独自の理論
★★★★☆
まず、学校文法(橋本文法)について、説明し、疑問を呈しています。 次に、国文法について、橋本進吉氏、時枝誠記氏、大野晋氏の業績を、批判を交えて解説しています。 その後、「句 phrase 」「群 group 」「相 aspect 」「時制 tense 」「ムード mood 」など、英文法にもある概念を用いて、自説を展開しています。 主語 subject を省略できる、語順 word order がかなり自由、読点の打ち方 punctuation に規則がないなど、あいまいな日本語の構造を体系化する試みで、面白いです。
本書を読んで、「主題 theme (話題 topic )」という概念 concept を、初めて知りました。 「主題」とは、解説すべき対象として提示された成分です。「主題」について述べている部分を「解説」といいます。
例文: 太郎は花子を次郎に紹介した。 「太郎は」は主題、「花子を次郎に紹介した」は解説です。
象は鼻が長い。 「像は」は主題、「鼻が長い」は解説です。
主題がない、無題文(現象文)もあります。
例文: 雨が降っている。
日本語、朝鮮語、中国語などは、主語を重視しない主題優勢言語 topic-prominent language 、英語、フランス語、ドイツ語などは、主語優勢言語 subject-prominent language だそうです。日本語では、「主題」は、話題マーカー topic marker としての係助詞「ハ」で示すそうです。 中国語では、語順で示します。
本書を読んで、「主題 theme (話題 topic )」という概念 concept を、初めて知りました。 「主題」とは、解説すべき対象として提示された成分です。「主題」について述べている部分を「解説」といいます。
例文: 太郎は花子を次郎に紹介した。 「太郎は」は主題、「花子を次郎に紹介した」は解説です。
象は鼻が長い。 「像は」は主題、「鼻が長い」は解説です。
主題がない、無題文(現象文)もあります。
例文: 雨が降っている。
日本語、朝鮮語、中国語などは、主語を重視しない主題優勢言語 topic-prominent language 、英語、フランス語、ドイツ語などは、主語優勢言語 subject-prominent language だそうです。日本語では、「主題」は、話題マーカー topic marker としての係助詞「ハ」で示すそうです。 中国語では、語順で示します。
日本語の「しくみ」が「わかる」本
★★★☆☆
中学校のときに習う日本語の「しくみ」(=日本語文法)って何か変じゃない?っていうところから始まって、だったらこう考えれば「わかる」んだ、ということを話し口調で書いてくれています。ユーモアを入れながら軽妙な語りで、すらすら読めるのがいいところです。ただ、印象として「独り言」のような本です。本文の下に補足がついているんですが、「そんなこと聞いてないよ〜」という感じが幾度かするものだと思います。あと、「しくみ」が「わかる」というと、日本語の全体像が分かるような気がしてしまいますが、そのような期待は持たないほうがよいようです。教科書的な見方/一般的な見方/専門家の見方、をちょっと立ち止まって考えるというには良い本です。そういうわけで、初心者向けの本ではなく、日本語文法や言語学に興味がある人に向いている本だと思います。