ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲
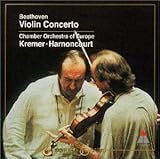
古典解釈で異色を放つ指揮者アーノンクールの発案なのか、個性的バイオリン奏者と知られるクレーメルの申し入れなのかは判然としませんが、この2人ではありそうなことだ思われます。
愛蔵版としての名演CDとしてはお勧め出来ませんが、偶に聴くオプションと言いますか変わった代替演奏としては良いかも知れません。
クレーメルもアーノンクールも、現代の聴き手に積極的な独自解釈をしてのメッセージを発していると思えば納得が行かないことはありません。
この演奏はYouTubeで聴くことが出来ませんが・・やはり異質なので愛好者が極めて少ないと言うことでしょうか!
そもそもの話からしよう。ベートーヴェンはヴァイオリン協奏曲を1曲しか作曲しなかった。それはベートーヴェンがその1曲の完成度に完璧といえる自信を持っていたからだと思われる。だがベートーヴェンは自作のヴァイオリン協奏曲にカデンツァを書かなかった。奏者の仕事に残したのである。現在最もよく聴かれる「よく出来た」カデンツァはクライスラーのものである。しかし、ここで妙なスコアが残ることになる。自分のヴァイオリン協奏曲をいたく気に入ったベートーヴェンはこれを「ピアノ協奏曲」に編曲した。そして「ピアニスト」でもあったベートーヴェンはこちらにはカデンツァを遺した。つまりその部分は「奏者」としての仕事を後世に遺したのである。
クレーメルの発案は、このベートーヴェンが「ピアノのために」書いたカデンツァを「ヴァイオリン協奏曲」の演奏に用いてしまおうというものである。しかし、これをそのままヴァイオリンで弾く、というほど単純ではない。なんと、このクレーメル版のカデンツァ、いきなり「ピアノ」が登場する。ヴァイオリン協奏曲のカデンツァがピアノ!と驚いていると、こんどはそこにクレーメルがヴァイオリンで旋律を「どうだい」といった気配たっぷりに奏でる。そして、このピアノ版カデンツァではティンパニが活躍する(一説では戦争のイメージとも考えられている)。なので、いっときはピアノ、ティンパニ、ヴァイオリンが繰り広げるなんとも楽しげな世界となる。さらには第3楽章のカデンツァでも、またまたピアノが出てくる。
この演奏と録音をどう捕らえるかはもちろん聴く側の自由だけれど、私はとても楽しいと感じた。何もスコア通りにやるのが全てではない。かのベートーヴェン自身が「さらに美しいために破りえぬ規則は何一つない」と述べた革命家であったことを考えると、むしろ今の風潮はこのような試みを安易に咎め過ぎるくらいだと思う。だからこそ、クレーメルとアーノンクールという権威であり大家である二人がこのような試みをこの時代にやったことに大きな意味があると思う。
最後になったがこのころのクレーメルの弾きぶりは全般にロマンティック。なかなかたっぷりとした歌いまわしで、こちらも堪能できる。
クレーメルの演奏は実演で、15年前くらいに聞いたことがあるのだが(その時分の録音のようだが)、彼の自由闊達さからしてかような解釈もありであろう。
もはや、PCやウエッブが跋扈する21世紀にベートーベンやモーツアルトを視聴していることを、われわれは忘れてはいけないのだろう。
こんな時代遅れの解釈をベートーヴェンだとするのは間違いである。
ロマン派の開拓者であるベートーヴェンを古典派に逆戻しにしてどうなるのか。
アンノンクールもクレーメルも恐らくこれで音楽界からの信用を無くしている。
極めて不自然な演奏となっている。
歴史的駄解釈の一つ・・・・・
相互の衷心からの尊敬に裏打ちされたクレーメルとアーノンクールの共演は、多くの衝撃を聴衆に与えてきたが、このベートーベンは衝撃に加え、広範な聴衆の支持を得た演奏である。
まず印象的なのは、独奏バイオリンが名技主義と決別し、ひたすらリリックに歌いるづけることである。アーノンクールとの入念な検討の成果であろうが、かつてないほど独奏パートは<本質的な音>と<装飾的な音>に分析されて、再構成されている。従って基本的な旋律の歌い方は、古楽器奏者がバロック音楽においてする解釈と極めて接近する。確かにビブラートは、それほど抑制されていないが、歴史的奏法の基本に立ち戻って、アーティキュレーションとして効果的で必要な箇所に施されている。
ソロパートからわい雑物が排除され、表現が純化され、結果的に透明感とリリシズムが強調されることになった。これはウィーンの古いバイオリンの大家の表現に通じる印象があり、その意味でアーノンクールの確信犯的誘導?によるのかもしれない。
オーケストラは、ベートーベン交響曲全集でアーノンクールの意図を十全に表現したヨーロッパ室内管弦楽団を起用し、万全を期している。見事な運動機能とアンサンブル力であり、それはひとえに楽団員の指揮者に対する尊敬に由来するといってよかろう。いかなる一瞬をとっても透徹した響きに満ち、すべてのテクスチュアは自然な明晰さを持つ。ベートーベンの力感と佇立する巨大さは全く損なわれていないのに、ひたすらな整然・調和・透明が顕著である。
以上から出来上がった演奏は、総体として、ベートーベンから(20世紀後半の聴衆が気付かぬうちに混入していた)後期ロマン派的要素を払拭した。筆者はこの境地を「ひたすらな透明感がもたらした、ウィーン郊外の野の春の若草の朝露の香り」と形容したい。その意味で(アーノンクールの理解における)真に初期ロマン派的なリリシズムに満ちた演奏となった(モーツァルトとベートーベンはやはり違うのだ!)
カデンツァについて付言すると、作曲家自身の手になるこの曲のピアノ協奏曲版のカデンツァを基に、クレーメルが創作したもので、発売当時大変な賛否両論を起こした(カデンツァが、頻用されている<お定まり>のものだったら、このCDはもっと多くのレコード賞を受賞したであろう、とまで言われた)。もともとクレーメルはこの曲のカデンツァにはこだわりを持っていて、現代の作曲家のものを演奏したりしていた。
さて現在の聴き手は、10年前の(不毛の?)論争について、どう感じられるであろうか。はたしてカデンツァだけを理由に、レコード賞を逃すような非(反?)音楽的なものであったか否か・・・