Jesus' Son
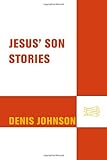
「ダンダン」は銃で撃たれた被害者を主人公が病院まで連れていこうとする話。だがその動機はかなり不純だ。「俺は命の恩人になりたかった。最後までマックイーンを見捨てずに医者に連れていけば、きっとみんな、俺の話で盛り上がるだろう。そう、俺はヒーローになりたかった」。ところがそのあとの「ひとちがい」という話では、彼自身も痛ましい刺し傷を負うことになる。だがここでも彼は、ドラッグを盗んだ相手に仕返ししようとしたはずが、実際は事件とは無関係の家族を震え上がらせるだけで終わってしまう。
本書の話はどれもとりとめがなく、中には起承転結をまるで無視した話さえある。にもかかわらずつい夢中で読んでしまう1冊だ。どこか退廃的な美しさが漂う文章からは、詩人としても一流であるデニス・ジョンソンの力量が伝わってくる。どのページも宝石のようなまばゆい輝きを放つ言葉のオンパレードだ。
「俺にはひとつひとつの雨粒の名前までわかる。何かが起きる前にその気配を感じとれる。だからあの車がスピードを落とす前から、きっと俺の前で停車するだろうってことがわかっていた。楽しそうな家族の話し声を耳にした瞬間、俺たちが嵐に巻き込まれて事故にあうだろうってことがわかった」
本書の短編はどれも出色のできばえで、おどろくほど鮮やかに人生の一瞬を切り取ってみせる。たとえば、喪失の痛みに苦しむ相手を目前にした主人公がはじめて生きる喜びをかみしめる「ヒッチハイク中の事故」。
「廊下の向こう側から男の妻がやってきた。美人で情熱的な感じの女だ。彼女はまだ夫が死んだことを知らない…あっ、なんて大きな悲鳴なんだ! 彼女の金切り声はワシの鋭い鳴き声に似ていた。俺は生きている。彼女の悲鳴を聞いている。そう思ったとたん、俺はたまらなく幸せな気分になった。そうか、これまでずっと俺はこんな感動を探し求めていたんだ」
また「仕事」では、主人公とその知り合いが想像を絶するような光景に遭遇する。ドラッグ保管場所だった家が浸水、そこから警官を「救出」しようとしていたときのことだ。彼らは1人の美しい裸の女が川上に向かってパラグライダーで飛んで行くのを目撃し言葉を失う。のちに主人公は、その家の持ち主が落ちぶれはてたかつての彼の共犯者だったこと、そしてあの女が彼と離婚寸前の妻だったことを知り、こう思う。
「これだけは言える。ウェインは妻に対しても家に対しても夢みたいな世界を描いていた。そして俺はあの日、その世界にちょっと立ち入っただけなんだ」
本書の読者もこれに似た世界を経験することだろう。ブコウスキーというよりはジュネに似たタイプの作家デニス・ジョンソンは、醒めることのない奇妙な魂の夢の中へといつしか読者をひきずりこむ達人である。(Langdon Cook, Amazon.com)
デニス・ジョンソンが描く世界像はどこか奇妙である。しかしそれは、他の多くのアンダーグラウンド小説に見うけられる、わざとらしく暴力的であったり過度の性的な描写に溢れたものとは明らかな一線を画している。
彼の世界は、どうすることも出来ない運命の皮肉ないたずらに支配されているようだ。確かに語り手である主人公は酒におぼれ、ドラッグを常習し、街をあてもなくさまよい、実りのない女性遍歴を重ねるのだが、彼の精神は不思議とある種の純真さを失わない。その様子は特に最後の章の「ビバリー・ホーム」に現れている。老人や、精神障害を持った人々のための保護施設である「ビバリー・ホーム」で働くことに主人公はやっと帰属の感情を抱くことになる。デニス・ジョンソンがよく取り上げる人間の生と死の問題に、主人公はここでも直面せざるを得ないのだ。 果たして、そこが彼にとって最終的に行きついた場所であるとは言えないかもしれない。しかし、Jesus’ Sonの主人公は自分に降りかかる、もしくは自分で招いた災難になすすべもなく翻弄されながらも、常に「普通の人」でありつづける。ブラック・ユーモアに満ち溢れた不幸な出来事にとまどい、泣き、自分を嫌悪したり、時に友達と語り合い笑うのだ。
アメリカの欲望と、人生の失敗の苦い影。主人公がそのなかをさまよいながらも自分に対して正直である姿に救われる思いがした。