風雲児たち (7) (SPコミックス)
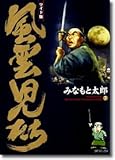
価格: ¥680
カテゴリ: コミック
ブランド: リイド社
関連商品
困難はより弱い者達に襲いかかる
★★★★★
7巻から8巻にかけては天明の大地震、浅間山の大噴火と
それに続く天明の大飢饉が時代背景として描かれます。
江戸での生活は苦しくなるものの奥羽地方の飢餓の
現状はとてもピンとは来ない他人事。
10万人の餓死者は出ても、武士階級の餓死者はゼロ。
江戸にフランス革命は起きず、ただただ弱いものが
死んで行く・・・・これは現代のどこか、日本の近くの国でも
現実に起きていることと似ているような気がします。
最近芥川賞を受賞した女性作家が、小学生の時に教師から
「誕生日おめでとう」といわれた際に
「誕生日を迎えるとはつまり死に近づくことだから
全然めでたくなんかない!」と噛み付いて教室の空気を
凍らしたというエピソードを披露していました。
その後この作家の考えがどう変化したかは不明ですが、
豊かさは人が死と常に隣りあわせであることや
天候不順や農作物の出来具合から人はいつでも貧困状態に陥り
命を落としかねないという事実を見えないものにしてしまう。
当時からすればとてつもない豊かさを享受している現代日本でも
その本質は変わらないはずだということを頭の片隅に入れて
今後も読み進めていきたい。
それに続く天明の大飢饉が時代背景として描かれます。
江戸での生活は苦しくなるものの奥羽地方の飢餓の
現状はとてもピンとは来ない他人事。
10万人の餓死者は出ても、武士階級の餓死者はゼロ。
江戸にフランス革命は起きず、ただただ弱いものが
死んで行く・・・・これは現代のどこか、日本の近くの国でも
現実に起きていることと似ているような気がします。
最近芥川賞を受賞した女性作家が、小学生の時に教師から
「誕生日おめでとう」といわれた際に
「誕生日を迎えるとはつまり死に近づくことだから
全然めでたくなんかない!」と噛み付いて教室の空気を
凍らしたというエピソードを披露していました。
その後この作家の考えがどう変化したかは不明ですが、
豊かさは人が死と常に隣りあわせであることや
天候不順や農作物の出来具合から人はいつでも貧困状態に陥り
命を落としかねないという事実を見えないものにしてしまう。
当時からすればとてつもない豊かさを享受している現代日本でも
その本質は変わらないはずだということを頭の片隅に入れて
今後も読み進めていきたい。
たび重なる天災や理不尽な運命に抗して
★★★★★
天明三(1783)年、浅間山が史上最大の大噴火を起こしていた頃、神昌丸の船長・大黒屋
光太夫は、八ヶ月に及ぶ漂流のすえ、アリューシャン列島の一つ、アムチトカ島に漂着した。
奇しくも、同年一月には、仙台藩医・工藤平助が、類いまれな見識に基づき、
当時最高レベルの北方資料となる『赤蝦夷風説考』を完全脱稿させていた。
一方、蘭学の分野では、杉田玄白と前野良沢の名前から一字ずつもらい、改名した
大槻玄沢が、日本最初のオランダ語入門書『蘭学楷梯』を著し、西洋画では、司馬
江漢が、銅版画を創り上げることとなる。
しかしその頃、奥州は、牙を剥きはじめた天明の大飢饉により、
荒廃の一途を辿ろうとしていた――。
天明三(1783)年、浅間山が史上最大の大噴火を起こしていた頃、神昌丸の船長・大黒屋
光太夫は、八ヶ月に及ぶ漂流のすえ、アリューシャン列島の一つ、アムチトカ島に漂着した。
奇しくも、同年一月には、仙台藩医・工藤平助が、類いまれな見識に基づき、
当時最高レベルの北方資料となる『赤蝦夷風説考』を完全脱稿させていた。
一方、蘭学の分野では、杉田玄白と前野良沢の名前から一字ずつもらい、改名した
大槻玄沢が、日本最初のオランダ語入門書『蘭学楷梯』を著し、西洋画では、司馬
江漢が、銅版画を創り上げることとなる。
しかしその頃、奥州は、牙を剥きはじめた天明の大飢饉により、
荒廃の一途を辿ろうとしていた――。
風雲児たちを襲う暗い影
★★★★☆
この巻は全体に暗い雰囲気に終始する。
相次ぐ飢饉と一揆、大地震に火山の大噴火。
停滞した時代を変えようと、田沼意次、林子平らはそれぞれ奮闘するが、
時代が早すぎたのか理解をえられず、なかなか成果はあがらない。
この時代の日本は、ますます泥沼に向かっていってしまうのだが、
もうひとつの全く別のドラマが、この巻からスタートする。
それは伊勢の商船の船頭、大黒屋光太夫のアリューシャン列島への漂着だ。
彼らはここで原住民に加えてロシア人に出会うわけだが、
次の巻以降に続く彼らの大冒険の序章となる。
物語とは直接関係ないが、大黒屋光太夫の話の冒頭で紹介された
江戸時代までの日本の造船技術に関するエピソードは興味深かった。
この巻以降、風雲児たちには苦難が多く降りかかる。
相次ぐ飢饉と一揆、大地震に火山の大噴火。
停滞した時代を変えようと、田沼意次、林子平らはそれぞれ奮闘するが、
時代が早すぎたのか理解をえられず、なかなか成果はあがらない。
この時代の日本は、ますます泥沼に向かっていってしまうのだが、
もうひとつの全く別のドラマが、この巻からスタートする。
それは伊勢の商船の船頭、大黒屋光太夫のアリューシャン列島への漂着だ。
彼らはここで原住民に加えてロシア人に出会うわけだが、
次の巻以降に続く彼らの大冒険の序章となる。
物語とは直接関係ないが、大黒屋光太夫の話の冒頭で紹介された
江戸時代までの日本の造船技術に関するエピソードは興味深かった。
この巻以降、風雲児たちには苦難が多く降りかかる。
内に外に北に南に困難に立ち向かう風雲児たち
★★★★★
風雲児達の逆風の時代は続く。嫁さん二人もろうた高山彦九郎は苦難の全国行脚、林子平の意見は仙台藩に受け入れられず。天命の大飢饉に浅間山噴火は上州はむろん庶民生活を直撃、印旛沼干拓に執念を燃やす田沼意次・意知親子を苦境に立たせる。松平定信は虎視眈々と遠く白河の地に潜む。
そのころ、伊勢の商船・神昌丸が遠州駿河沖で遭難、大海原を漂流していた。船長は大黒屋光太夫。8ヶ月もの漂流を経て流れ着いたのは故郷の伊勢ではなく現ロシア領のアリューシャン諸島であった。ここより彼らの日本を目指した長大な冒険が始まるのである。
蘭学第二世代の大槻玄沢がオランダ語入門書「蘭学楷梯」を、司馬江漢は銅版画を完成させる。苦難が続く時代において、ゆっくりとだが確実に時代の歩を進めて行くものがいることも作者はしっかりと描いている。
そのころ、伊勢の商船・神昌丸が遠州駿河沖で遭難、大海原を漂流していた。船長は大黒屋光太夫。8ヶ月もの漂流を経て流れ着いたのは故郷の伊勢ではなく現ロシア領のアリューシャン諸島であった。ここより彼らの日本を目指した長大な冒険が始まるのである。
蘭学第二世代の大槻玄沢がオランダ語入門書「蘭学楷梯」を、司馬江漢は銅版画を完成させる。苦難が続く時代において、ゆっくりとだが確実に時代の歩を進めて行くものがいることも作者はしっかりと描いている。
幕末にそれほどは…?
★★★★☆
大黒屋光太夫漂流や高山彦九郎全国行脚、
それほど幕末に重大な影響をあたえたかは微妙なライン。
楽しいのは楽しいが。
それほど幕末に重大な影響をあたえたかは微妙なライン。
楽しいのは楽しいが。