風雲児たち (10) (SPコミックス)
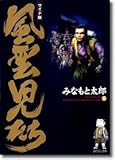
価格: ¥680
カテゴリ: コミック
ブランド: リイド社
関連商品
大黒屋光太夫の果てなき旅路と寛政の改革
★★★★★
カムチャツカからオホーツクに入港した大黒屋光太夫一行は、
日本に帰国するため、ヤクーツク、さらにはイルクーツクへと
厳冬のシベリア大陸を旅する。
しかし、命からがら、やっとイルクーツクに辿り着いた彼らを
持っていたのは、日本語学校の教師として永住せよ、という
無情な通達だった。
失意に沈む光太夫だったが、博物学者ラックスマンとの出会いが光明をもたらす。
一方、日本では年号が寛政と改まり、松平定信の寛政の改革が始動する。
厳格な身分差別を奨励する朱子学以外の「異学」が
禁止されるだけでなく、蘭法「医学」も一切禁じられた。
国際情勢を無視し、ひたすら農工商を抑圧することで、江戸幕府の
安寧だけを守ろうとした定信の改革は、現実に対応しきれず迷走し
その矛先を、時代の先覚者たる林子平、高山彦九郎、最上徳内ら
へと向けていくことになる――。
日本に帰国するため、ヤクーツク、さらにはイルクーツクへと
厳冬のシベリア大陸を旅する。
しかし、命からがら、やっとイルクーツクに辿り着いた彼らを
持っていたのは、日本語学校の教師として永住せよ、という
無情な通達だった。
失意に沈む光太夫だったが、博物学者ラックスマンとの出会いが光明をもたらす。
一方、日本では年号が寛政と改まり、松平定信の寛政の改革が始動する。
厳格な身分差別を奨励する朱子学以外の「異学」が
禁止されるだけでなく、蘭法「医学」も一切禁じられた。
国際情勢を無視し、ひたすら農工商を抑圧することで、江戸幕府の
安寧だけを守ろうとした定信の改革は、現実に対応しきれず迷走し
その矛先を、時代の先覚者たる林子平、高山彦九郎、最上徳内ら
へと向けていくことになる――。
鎖国の世の大ロシア紀行
★★★★☆
この巻のハイライトは、大黒屋光太夫のロシア大紀行。
日本に帰りたい気持ちとは裏腹に、
オホーツクから遥か西へ1,000km以上離れたイルクーツクへ行かされる。
実はこの時代にロシアを旅した「漂流日本人」は、
光太夫一行以外にも何組か居たことがこの巻で明らかになる。
しかし、それらロシアの地に埋もれた日本人と比べても光太夫は際立っていた。
ロシアでの出来事を克明に記録していたこと、
船乗り集団をまとめる類稀なリーダーシップがあったこと、
積極的にロシア語を覚えロシア人と交流を持ったこと、
そして何よりも「日本へ帰る」と言う断固とした意思があったこと。
これら光太夫の能力のおかげで、今日の我々はこの「風雲児たち」や
井上靖の「おろしや国酔夢譚」のような物語を楽しみ、
この時代にしてここまでコスモポリタンな人物を生み出した民族性に
誇りを感じていられるのだ。
(「文字が書ける船乗り」は、当時のヨーロッパでも珍しい存在だったらしい)
光太夫の旅は、次の巻にも続く。
日本に帰りたい気持ちとは裏腹に、
オホーツクから遥か西へ1,000km以上離れたイルクーツクへ行かされる。
実はこの時代にロシアを旅した「漂流日本人」は、
光太夫一行以外にも何組か居たことがこの巻で明らかになる。
しかし、それらロシアの地に埋もれた日本人と比べても光太夫は際立っていた。
ロシアでの出来事を克明に記録していたこと、
船乗り集団をまとめる類稀なリーダーシップがあったこと、
積極的にロシア語を覚えロシア人と交流を持ったこと、
そして何よりも「日本へ帰る」と言う断固とした意思があったこと。
これら光太夫の能力のおかげで、今日の我々はこの「風雲児たち」や
井上靖の「おろしや国酔夢譚」のような物語を楽しみ、
この時代にしてここまでコスモポリタンな人物を生み出した民族性に
誇りを感じていられるのだ。
(「文字が書ける船乗り」は、当時のヨーロッパでも珍しい存在だったらしい)
光太夫の旅は、次の巻にも続く。
フランス革命の時代、日本はどうだったか
★★★★★
苦難の旅のすえ、光太夫はイルクーツクへ着く。そこで彼らを待ち受けていたのは日本語教師になれというロシア側の通告だった。それはイコール帰国を認めないことである。困った彼らはフィンランドの博物学者ラックスマンを頼る。彼の口から聞かされる中川淳庵や桂川甫周の話。ツンベリーと彼らの交際は回りまわって光太夫達の耳に届いていたことに驚嘆する。
国内では、松平定信による寛政の改革が吹き荒れ、窒息しそうなまでに淀んだ世相のなか、ロシアの脅威がついに江戸城まで届く。田沼の先見性に嫉妬した定信は、あろうことか蝦夷調査に向かわせた青島俊蔵と最上徳内を捕縛する。疎まれた林子平も命を狙われ、彦九郎も故郷から去っていく。
暴走する朱子学観念論は現実を見ようとする者達を徹底的に弾圧する。この先の蛮社の獄や安政の大獄等何度も繰り返される。外に目を向けない愚かさに嘆息するしかない。
国内では、松平定信による寛政の改革が吹き荒れ、窒息しそうなまでに淀んだ世相のなか、ロシアの脅威がついに江戸城まで届く。田沼の先見性に嫉妬した定信は、あろうことか蝦夷調査に向かわせた青島俊蔵と最上徳内を捕縛する。疎まれた林子平も命を狙われ、彦九郎も故郷から去っていく。
暴走する朱子学観念論は現実を見ようとする者達を徹底的に弾圧する。この先の蛮社の獄や安政の大獄等何度も繰り返される。外に目を向けない愚かさに嘆息するしかない。
北を舞台に人が時代に飲み込まれる
★★★★☆
大黒屋光太夫のロシアの話に最上徳内達の北海道探索。
描かれる当時の国内外の差。必死に行動する人々。
重苦しいながら、時代が古いながらもギャグが緩衝材として作用し、
楽しく読めます。幕末はまだまだ先ながら人は未来に続く種を蒔く。
描かれる当時の国内外の差。必死に行動する人々。
重苦しいながら、時代が古いながらもギャグが緩衝材として作用し、
楽しく読めます。幕末はまだまだ先ながら人は未来に続く種を蒔く。
絶望的状況の中で何をすればいいか
★★★★★
大飢饉が日本中を被った天明年間の歴史を書くこの巻は、それでも人間には笑いが大切だと言うことを伝えてくれる、作者の漫画家魂のあふれ出ている名作です。しかし、笑いのための苦労には事欠かない漫画家だけに、笑いの陰に苦労があることを痛ましいほどに描くのです。人のために泥を被る事ができた人がいたことをけして忘れてはいけないのだと思い知らされる作品です。努力の価値、行動の価値は、その人の思想、業績ではなく。ではなんなのか?それをヒントを与えつつ、考えさせてくれる「風雲児たち」の一つのピークをなす巻です。絶望的な状況の中で何をすればいいか、少なくとも絶望しないことでしょうが、それ以上の何かを教えてくれる本です。