回天の門 (文春文庫)
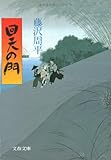
価格: ¥790
カテゴリ: 文庫
ブランド: 文藝春秋
もともとのタイトルは『回天の門 草莽の人・清河八郎』
★★★★★
清河八郎は、羽州清川の人。江戸に上り、文武両道を修め、幕閣に、佐幕のための浪士組の結成を建白、
認められ新徴組を結成。京に上るが、突然尊皇を唱え、反発した近藤勇らは、新撰組を結成する。
この変節のため、清河は、策士、傲岸不遜、山師などの悪評をいただく。
本当にそうだったのか、同郷の作家藤沢周平が真っ向から異論を唱え、清河を描いた。
単行本発行時のタイトルは『回天の門 草莽の人・清河八郎』だったが、文庫本化にさいして、
「草莽の人・清河八郎」の部分が除かれた。なぜなのかは書いていない。
憶測だが、清河の世上の人気の低さや、
「草莽の人」である(政治的に立ち上がった野にある名もない志士たちの意,太平洋戦争後は,テロリストの意味も持った)ということが
清河の人物像としては受け入れられないと判断した故の結論だったのだろうか。
清河を描いた人物には、司馬遼太郎、柴田錬三郎、海音寺潮五郎、大川周明と、そうそうたる有名人が並ぶが、
その中で最も清河を愛しているのは藤沢周平である。愛しているだけに取材が丹念で、
その分疑問が起こらないので、すらすら読める。
清河の行動に、当時のぺリー来航、安政の大獄などの誰でも知っている幕末の出来事が、
オーバーラップして描かれる。
この本の真骨頂のひとつは、それら歴史が、清河にどう伝わったかを描く点だ。
明治政府がかいたものでもなく、戦後の教科書でもなく、歴史は、清河たち在野の人物にどう伝わったのか。
それもきわめて興味深い。
認められ新徴組を結成。京に上るが、突然尊皇を唱え、反発した近藤勇らは、新撰組を結成する。
この変節のため、清河は、策士、傲岸不遜、山師などの悪評をいただく。
本当にそうだったのか、同郷の作家藤沢周平が真っ向から異論を唱え、清河を描いた。
単行本発行時のタイトルは『回天の門 草莽の人・清河八郎』だったが、文庫本化にさいして、
「草莽の人・清河八郎」の部分が除かれた。なぜなのかは書いていない。
憶測だが、清河の世上の人気の低さや、
「草莽の人」である(政治的に立ち上がった野にある名もない志士たちの意,太平洋戦争後は,テロリストの意味も持った)ということが
清河の人物像としては受け入れられないと判断した故の結論だったのだろうか。
清河を描いた人物には、司馬遼太郎、柴田錬三郎、海音寺潮五郎、大川周明と、そうそうたる有名人が並ぶが、
その中で最も清河を愛しているのは藤沢周平である。愛しているだけに取材が丹念で、
その分疑問が起こらないので、すらすら読める。
清河の行動に、当時のぺリー来航、安政の大獄などの誰でも知っている幕末の出来事が、
オーバーラップして描かれる。
この本の真骨頂のひとつは、それら歴史が、清河にどう伝わったかを描く点だ。
明治政府がかいたものでもなく、戦後の教科書でもなく、歴史は、清河たち在野の人物にどう伝わったのか。
それもきわめて興味深い。
スポットライトを当てる
★★★★☆
幕末の志士、清河八郎を主人公にした物語です。清河八郎には、紹介文で書いているように「変節漢」などという悪評が付きまとっています。しかし藤沢氏はそれに疑問を感じ、清河八郎の生涯を丹念に追っていき、その一貫とした意思と生き様を描いています。
この物語で清河八郎が志士として活動し始めるのは後半に入ってからです。それまでは淡々と時代背景が書かれたり、文武両道塾の開設にむけての八郎の努力が描かれています。この物語の半分は幕末の解説書と言っても過言ではないかもしれません。幕末の志士の活動を、新撰組などの華やかさとは別の角度から知りたいという方におすすめです。
この物語で清河八郎が志士として活動し始めるのは後半に入ってからです。それまでは淡々と時代背景が書かれたり、文武両道塾の開設にむけての八郎の努力が描かれています。この物語の半分は幕末の解説書と言っても過言ではないかもしれません。幕末の志士の活動を、新撰組などの華やかさとは別の角度から知りたいという方におすすめです。
本の厚さ分だけ 面白さ満載!
★★★★★
世の中に、こんな分厚い文庫本があるだろうか?否、それがし 見たことありませぬ。
2.5cmの超ど分厚い文庫本。
しかし、これが面白くてどんどん読めちゃうのである。「日本史」が大嫌いな私でも。
まさに、「清河八郎」物語。
幕末から明治、世の中が一変する頃、
官途へ一片の野心さえ持たぬ草莽(そうもう)の志士がいた。
それは、庄内、酒屋の遊郭狂いの跡取りドラ息子。斎藤元司=後の「清河八郎」。
「維新回天」の夢を一途に追うて生きた清冽な男の生涯。
幕末の15年、こんな天下分け目のものすごいことがこの世にあったのか?と素直に驚いた。「清河八郎? 誰?」ってな感じで、聞いた事など全くありませんでしたが、「へー、実在の人物なんだー」と。読んでいくうちに嵌っちゃいました。
昔 学校の「日本史」で習った言葉が次々に出てきました。
大政奉還1867・明治維新、ペリー来航1853、鎖国、アヘン戦争1840、江戸大地震1855などなど、登場人物も続々。思わず昔の年表を引っ張り出し、確認しながら読んだ。
・「回天」・・時勢を一変させること。衰えた国政を元に返すこと。
・「志士」・・りっぱな志をもつ人。身を捨てて国事に尽くす人。
こんな初めて聞く言葉も勉強しちゃいました。
しかし、驚くのは、
こんな分厚い本でも、最後までドキドキ・はらはらしたこと。
特に最後の10ページから巻末。
「この本が終わるということは、清河八郎が殺されちゃうってことか?」などと、結末までいくことが嫌になりました。
でも、しかし、凄い人物だ。
山形県にある「清河八郎記念館」に行って見たくなったのはそれがしだけか?
■お薦め度:★★★★★(これは120%面白い本です)
2.5cmの超ど分厚い文庫本。
しかし、これが面白くてどんどん読めちゃうのである。「日本史」が大嫌いな私でも。
まさに、「清河八郎」物語。
幕末から明治、世の中が一変する頃、
官途へ一片の野心さえ持たぬ草莽(そうもう)の志士がいた。
それは、庄内、酒屋の遊郭狂いの跡取りドラ息子。斎藤元司=後の「清河八郎」。
「維新回天」の夢を一途に追うて生きた清冽な男の生涯。
幕末の15年、こんな天下分け目のものすごいことがこの世にあったのか?と素直に驚いた。「清河八郎? 誰?」ってな感じで、聞いた事など全くありませんでしたが、「へー、実在の人物なんだー」と。読んでいくうちに嵌っちゃいました。
昔 学校の「日本史」で習った言葉が次々に出てきました。
大政奉還1867・明治維新、ペリー来航1853、鎖国、アヘン戦争1840、江戸大地震1855などなど、登場人物も続々。思わず昔の年表を引っ張り出し、確認しながら読んだ。
・「回天」・・時勢を一変させること。衰えた国政を元に返すこと。
・「志士」・・りっぱな志をもつ人。身を捨てて国事に尽くす人。
こんな初めて聞く言葉も勉強しちゃいました。
しかし、驚くのは、
こんな分厚い本でも、最後までドキドキ・はらはらしたこと。
特に最後の10ページから巻末。
「この本が終わるということは、清河八郎が殺されちゃうってことか?」などと、結末までいくことが嫌になりました。
でも、しかし、凄い人物だ。
山形県にある「清河八郎記念館」に行って見たくなったのはそれがしだけか?
■お薦め度:★★★★★(これは120%面白い本です)
☆5つ
★★★★★
「魁がけてまたさきがけん死出の山 迷ひはせまじすめらぎの道」
司馬遼太郎作品をはじめとする多くの幕末小説や歴史ドラマで描かれてきた清河八郎は、正当な評価、少なくとも好意的な評価を受けて描かれたとは言い難い。
マシな描かれ方をしたところで、せいぜい「100年に一人の逸材であるにも関わらず、自身の才能を恃みすぎ、また策謀を用いすぎるために、ついには大きな仕事は出来ない」というところか。
一言で言えば、清河八郎は「イヤなヤツ」だ。
でも、これまで私はどうにも腑に落ちなかった。
何がって、「魁がけて」の辞世が。
どうしてもそんなイヤなヤツの辞世とは思えない。
もちろん、ノリで作った歌がたまたま辞世になってしまっただけとも考えられるけど、上記のイメージ通りの清河ならもっと小難しい、回りくどい、小賢しい歌ばかり作ってそうなものだ。
にも関わらず実際に遺されたのは、清清しさすら感じる直球ド真ん中のわかりやすい歌。
そのギャップをキレイに埋めてくれたのがこの作品でした。
まさに時代を先駆けた男の人生を丹念に、かつ淡々と、それでいて温かく描いています。
彼に対するイメージが180度変わる人もいるかもしれません。
幕末小説が好きな人は必読の一冊ですね。
司馬遼太郎作品をはじめとする多くの幕末小説や歴史ドラマで描かれてきた清河八郎は、正当な評価、少なくとも好意的な評価を受けて描かれたとは言い難い。
マシな描かれ方をしたところで、せいぜい「100年に一人の逸材であるにも関わらず、自身の才能を恃みすぎ、また策謀を用いすぎるために、ついには大きな仕事は出来ない」というところか。
一言で言えば、清河八郎は「イヤなヤツ」だ。
でも、これまで私はどうにも腑に落ちなかった。
何がって、「魁がけて」の辞世が。
どうしてもそんなイヤなヤツの辞世とは思えない。
もちろん、ノリで作った歌がたまたま辞世になってしまっただけとも考えられるけど、上記のイメージ通りの清河ならもっと小難しい、回りくどい、小賢しい歌ばかり作ってそうなものだ。
にも関わらず実際に遺されたのは、清清しさすら感じる直球ド真ん中のわかりやすい歌。
そのギャップをキレイに埋めてくれたのがこの作品でした。
まさに時代を先駆けた男の人生を丹念に、かつ淡々と、それでいて温かく描いています。
彼に対するイメージが180度変わる人もいるかもしれません。
幕末小説が好きな人は必読の一冊ですね。
幕末の最も早い時期を駆け抜けた男を丹念に描いた本です
★★★★☆
多くの草莽の志士たちによって、改革がなしとげられた幕末ですが、彼らの多くは、権力や資金もなく、自らの思想や弁舌によってしか、人々を動かすことができませんでした。そのため、時に、欺瞞に近いこともなさねばならず、後の人々から、策士・山師あるいは出世主義者と蔑視されることも多い彼らですが、そのような見方をされることの最も多い1人が清河八郎ではないでしょうか。著者は、八郎が残した著作等も引用しながら、彼の足跡を丹念にたどり、八郎自身の思想は首尾一貫したものであり、そのような見方が誤解であることを明らかにしていきます。
著者の市井物に代表されるような明るさはありませんが、幕末の最も早い時期を駆け抜けた男を通して、幕末の状況が描かれた本であり、幕末物の好きな方にお奨めしたい本です。
著者の市井物に代表されるような明るさはありませんが、幕末の最も早い時期を駆け抜けた男を通して、幕末の状況が描かれた本であり、幕末物の好きな方にお奨めしたい本です。